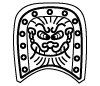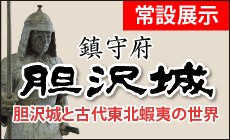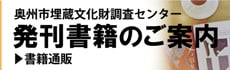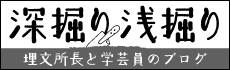シリーズ5◆玉貫遺跡の内耳鉄鍋

玉貫遺跡の内耳鉄鍋
玉貫遺跡は、水沢佐倉河字玉貫地内に位置します。発掘された12世紀の竪穴建物跡からは内耳鉄鍋が出土しました。
内耳鉄鍋とは、煮炊用などに使用する鉄鍋で、吊り下げて使用するために、内側に吊り下げ用の把手(吊耳)が付けられた鍋です。おそらくは、炉などで使用されたと考えられます。煮炊具は、古くから土師器の甕などが使われてきましたが、平安時代後期になると、土器が使用されなくなります。それに代わって内耳鉄鍋は、11~12世紀頃に登場し、岩手県内の遺跡でも出土例がみられるようになります。ただし、出土事例によってはその性格が異なるようです。それは、煮炊具で使用された鍋以外でも、古くから疫病で亡くなった人を葬るとき、その悪霊が出てこないように、かぶせて埋葬する風習があります。そのような鍋被り葬墓は、伝承として考えられてきましたが、発掘調査などや調査研究によってその事実が明らかになっています。