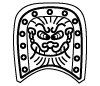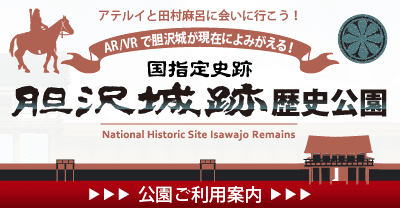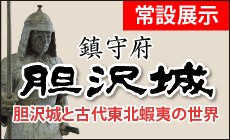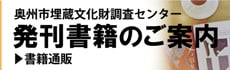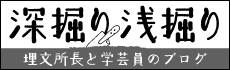新着情報とお知らせ
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-25
2024-03-24
2024-03-23
| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |
【奥州市内の遺跡包含地についてのお問合せにつきまして】 工事等に伴う、奥州市内の遺跡包含地についてのお問合せは、奥州市教育委員会 歴史遺産課(TEL0197-34-1316 FAX0197-35-7551)までお願いいたします。 |
<子ども元気プロジェクト>
体験学習会
親子で楽しむ縄文人なりきり体験
●日 時:2024年5月12日(日)
9:30~12:00
●会 場:埋文センター
●料 金:1人300円(保険料込)
●定 員:20人
定員となりました。
ただいまキャンセル待ちを受け付けております。
*ホームページで使用している文章・画像の著作権は全て一般財団法人奥州市文化振興財団 奥州市埋蔵文化財調査センターに帰属します。無断転載を禁止します。